第1話「事業承継」のはじめの一歩は「時間管理」ですよ。

⑴「事業承継」はいつから始めるといいの?
年齢で考えることがいいとは思いませんが、1つの指標として現社長の年齢で60歳を超えると事業承継の計画を立てて行動に移すことが必要だと考えられていて(中小企業庁では65歳以上の経営者にとって「目の前の課題」としています)、後継者は50歳までで考えておかなければ「考え方や順応性」、そして「新しい挑戦!」を考えたときに「IT化についていくことが厳しいかも…」といわれています。
社長の平均年齢は年々上昇し続けていて、2021年2月時点で60.1歳(帝国データバンク資料)。70歳以上で現役の社長も珍しくなく、だからと言って世代交代(事業承継)を先送りしても大丈夫というものではありません。
私のお客様にも80歳代で現役で不動産賃貸業をしている方や、50歳代で突然亡くなられたクリニックの院長もいらっしゃいます。私の父も52歳で亡くなりました(急性心筋梗塞でした)だから、年齢では決めるものではないと思っていますよ。
もう一つの統計で、後継者の不在率が65.1%で事業承継の準備が追い付いていない様子がうかがえます。また、60歳以上の経営者の50%が廃業を予定していて(2020年2月時点)、後継者不在の問題で3割近くを占めていました。
自分の代で会社を終わらせたくないのであれば、確実に事業承継ができる準備を考えておかなくてはいけませんね。
⑵事業承継の失敗を避けるためには
そもそも「自社の事業承継の手続きには何が必要なの?」も知らなければいけませんが、それは、また今度のお話として置いといて…
「自分の会社では事業承継を何のために(何を守るために)成功させなきゃいけないの?」と考えてみると、どんな答えが出てくるでしょうか?
事業承継は「会社が作り上げたものを守るために」とか、「信用を落とさず将来も必要とされ、仕事をいただき続けるために」必要ですが、具体的には社長の肩書の移動や財産の移動、そして働く人や技術、理念などの知的資産までも丁寧に引き継ぐことが重要です。
時間もかかることですし、また、社長の交代は「三方よし(従業員・金融機関を含む取引先など・自身を含めた家族や親族が良好な関係でいられるように)」で進めていくことが必要です。
事業承継は積み上げてきた歴史もバトンタッチしていくので「社長になったときから歴史を刻む作業を始め、引継ぎの準備もはじまっている」ということになりますね。
これはまだ、事業承継の実務レベル(手続き)のスタートではないですが…。
⑶突然死対策から始める事業承継
私はBCP(事業継続計画)のサポートをするときには「社長の死亡」もパターンとして考えています。BCP(事業継続計画)とは簡単に言うと、どんな突発的な事象が起きても事業が止まらないように、あらかじめリスクを洗い出して対策し、発災直後でインフラが整っていない状態でも「動ける力」をつけるために必要な訓練(レベルはいっぱいありますよ)や行動マニュアルを用意したりするものです。
トップの不在が事業をストップさせてしまうことを考えると、司令塔である社長のバトンタッチがうまくいかなかった場合(事業承継の失敗)は事業が止まるリスクの1つととらえています。
⑷引継ぎの失敗には冷ややかですよ
「事業承継」の言葉はあまり使われていなくても「引継ぎしといて!」という言葉はどこの企業でも頻繁に使っていると思います。
業務の「引継ぎ」は会社の流れを止めないように、うまく歩みを進めていくためにするものですから、伝達(引継ぎ)がうまくできていなかったことで、お客様からお叱りを受けることや取引を停止されることもあります。

地震で業務がストップしてしまったら…「しかたがないな…」で許してくれる取引先もあるでしょうけれど、自社以外のどこの会社も被害がなかった(または少なかった)災害や事故、新型コロナのクラスターが発生した…なんていうのも同じように、「ちゃんと対策やってたの?」とか、「急いで他を手配しなきゃ…」と冷ややかな対応を目の当たりにすると思います。
引継ぎをする時間を惜しまないことや災害から立ち上がる時間を早くできるようにしておかなくてはいけません。
これは事業承継も同じことが言えて、周りは失敗しても助けてくれることはないでしょう。
⑸トップで止めてしまう結果
「事業承継? うちはまだまだ…」という社長も多いです。
「事業承継なんて人から言われてするもんじゃない!」という社長もいるし、「まだまだ現役で仕事ができるんだから交代は考えていない!」とか「まだまだ後継者が育っていないから…」とか「まだまだ…」の後に社長の色々な感情も入ってきます。
これは、事業承継の「手続き」のことだけしか見えていませんし、自分の気持ちを優先している状態です。後継者が会社を成長させていく時間やチャンスを奪っている場合があることに気づいていないかもしれません。(環境の変化も社会が進歩するスピードも、メチャクチャ速くなったと思いますよ)
それでは「社長の突然死や事故などの対策はしていますか?」と尋ねられるとどうでしょうか?(最近では、新型コロナで入院してしまうことを考えた社長もいると思います)
社長しか知らないパスワードのために決済ができなかったり、社長しか知らなかった約束に誰も対応せずに大きな取引がなくなってしまったり…
社長の突然死対策ができていれば、とりあえず業務を止めずに事業承継の手続きに動くための時間稼ぎ(その程度でしかありませんが…)ができます。
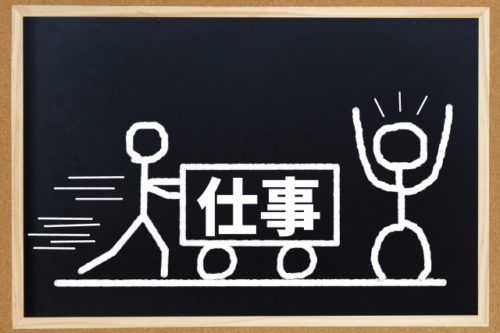
会社が止まってしまうことは「事業承継」自体できなくなるかもしれません。顧客(買い手)が離れたり、従業員(売り手)が離れたりすると会社の価値が下がってしまい、事業承継をする価値がなくなってしまうからです。
持論ですが「事業承継」は企業の一大イベントとして、短期集中型で考えると失敗したり、大きな妥協をしなければいけないことも出てきます。社長のご事情により「えい!やー!」で進めることもありますが、業務の引継ぎとして普段から意識する「リスクマネジメント」としておくと失敗や妥協の確率が格段に減ります。
⑹まずは社長業の棚卸しから
事業承継を後継者を決めることから進めるのではなく、いつでも社長の代行をしてもらえるように作業の棚卸しを進めていくといいですよ。
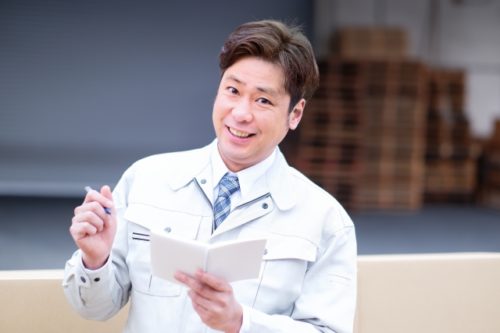
昨年、新型コロナで、宿泊療養になってしまった知人(社長)が「仕事ができる状態ではなく無力だった…」と教えてくれました。
その社長には、今後、同じようにお客様に迷惑をかけないよう、何を準備しておくとよいのか、「緊急事態」の引継ぎ作業を、できるだけ簡単にしておくにはどうするとよいのか、など棚卸し項目やチェックリストなどのツールを用意して段取りを説明しました。(すぐに「作業の棚卸しリスト」から作り始めていましたね)
肩書や資産の引継ぎ、持ち株率の調整、保証人の変更という大事な瞬間は、まだ先であっても、「失敗しちゃいけない項目」を普段使っているスケジュール帳に書いてみてはどうでしょうか。(お子さんがいれば、成長していく年齢(学年)も入れて横の直線にメモリをうった程度の年表にすると、社長がしておかなくてはいけない事柄やタイミングが見えたりしますよ。)
会社の5年後、10年後の未来をイメージして成長していきたいステップとその時のリスクを「見える化」しておくことは、どの社長にも必要な作業ですね。(年に1回更新するために、スケジュール帳を使うのもいいんですよ)
⑺事業承継には社長の引退後の生活も入れましょう!
肩書や資産の引継ぎは、1日や2日で片付く問題ではないのです。
その奥に沈んでいる家族間(親族間)の問題も解決できる時間が必要です。それを逆算できて意識するためにも、「社長の年表」を見える化してみましょう。(いつでも修正していいのですから)
リスクが毎年変わることも当然にあります。(だから気づいたときにパパッと修正できることが必要です。)
会社のリスクだけではなく、自分のリスクとして健康問題があるかもしれません。また、株主や相続人が変わったりすることもありますよね。

「社長の引退」である事業承継は家族にもかかわる問題です。突然社長業ができなくなったときの対策も考えておきましょう。(居心地のいい「居場所」はありますか?)
頭でわかっているだけではなく、書いて「見える化」しておくと意外に事業承継の準備が面倒ではなくなってくると思います。
一人親方の社長でも、従業員をたくさん抱えている社長でも作業は共通していることが多いです。
準備ができている事業承継と、突貫工事的な事業承継とでは、社長が大切にしてきた「想い」まで、きちんと伝わるのか大きく違うように思います。
ということで、今日は「事業承継のはじめの一歩は「時間管理」ですよ」についてお話ししました。

