第6回「緊急時の行動計画を決めるために知っておくこと」
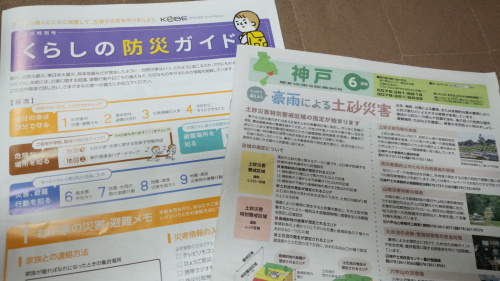 まずは「そこがどんな注意が必要な場所なのかを知ること!」ですね
まずは「そこがどんな注意が必要な場所なのかを知ること!」ですね![]()
私たちの住む日本は分かっているだけで活断層が約2,000もあります。
熊本地震の時には新たな活断層が見つかったとも言われていて、九州地方だけで把握しているのが20数か所あり、把握していないものも含めると、その3倍はあるのだそうです。
なので、地震対策はどこのおうちもしなければいけませんし、さらに、川の付近では洪水の危険があったり、山側では土砂災害も気にしなければいけません。
今の見た目で分かる風景から予測ができるものだけではなく、もっと昔…自分の住んでいるところはどんなところだったのか?
昔は農地であったら、水はけが悪いかもしれない。今、盛り土をして造成されているところは地震で沈下したり、液状化を起こしたりも考えられます。(兵庫県南部地震(1995)でもポートアイランドや六甲アイランド(埋立地)で大規模な液状化が発生しました)
大きな地震の際、盛り土による造成地で亀裂や地滑りなどが発生しやすく、家屋が無事でも敷地が「危険」なケースもあります。造成地の被害は、1995年の阪神大震災や2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災でも目立っていたようです。
現在はこのような造成地を政令指定都市では自治体のホームページで公表するようになっているようですが、その公表ができているのはおよそ4割程度だそうです。この度の熊本地震では熊本県は公表するための調査を始めたところだったそうですよ。
地名に水に関係する文字「川」「池」「浜」「津」「洲」「浦」「沢」「湧」などはもちろん、「浅」「深」「崎」「戸」「門」「田」「谷」なども海岸線や川の近く、低地、湿地帯などをあらわしていて、過去の津波到来や台風、豪雨などの増水時には大きな被害があったと考えられます。また「蛇」「竜」「龍」などが使われている地名には過去に大規模な土砂災害が発生しているケースが多く「蛇抜」「蛇崩」などの地名は土砂が流れていく様をあらわしているとされています。ただし、そこがすべて今でも危険かというと、そうでもなく、注意すべき崖や傾斜地そのものが開発によってなくなっている場合や、過去に水害が発生した場所であっても、自治体の水利工事によってそのリスクが大幅に減っているケースもありますので、このような名前のところに生活圏がある方は、そこが今大丈夫なのか補強されたりする工事があったのかなどを各自治体の窓口で聞いてみるといいと思います。
今日、わが家には神戸市から新しいハザードマップが配られてきました。今までに書いてなかった「避難所(小学校)に行くまでの経路に土砂災害の注意」が載っていました。個人的には前から危険そうなところとして調べていたので、私の子どもたちや、子どもの友達にも伝えていました。「学校に避難する時は、こっちの道から向かうこと」ってね![]()
地図上で見るのと、やはり現場を見て考えるのとでは違うな~![]() と思いました。
と思いました。
神戸市は各ご家庭にもハザードマップが手に入ります。そこで、どんな注意が必要なところに住んでいるのかなどは見れると思いますが、紙の上では分からないこともあります。たとえば、集合住宅の改装工事で数か月通れないことも行ってみてわかることもありますね。
実際に歩いて避難所まで行くことも時々しておくべきだと思いますよ![]()
さて、緊急時の行動計画を考えるには、どんな所なのかは知っておかなくてはならないということは…
そうです。自分の家だけではなく、学校やデイサービスなど家族が係る施設の場所も知っておかなくてはいけませんね。
住民には配布されるハザードマップだけでは圏外になってしまう、少し離れたところに通っている施設があれば、そこに係る自治体のホームページを調べたり、その他、インターネットで地震のゆれやすさを見ることもhttp://www.asahi.com/special/saigai_jiban/津波の被害想定を見ることなども情報を出している自治体は見られるようになっています。http://disaportal.gsi.go.jp/viewer/index.html?code=4)
南海トラフ地震の被害想定を調べられるところもあります。http://www.asahi.com/special/nankai_trough/
わが家では子どもたちが通うスイミングスクールの送迎バスは、行き道に約20分、山道を登り、川のふちを走るため、出来るだけ10分でも時間を作って私が送るようにしています。(帰りは5分で川のふちを通ることもないのでバスに乗せています)
自治体から配られるハザードマップでは圏外で分からないので、上記の検索をして調べると、南海トラフ地震が起こった場合、スイミングスクールのビルは浸水の被害を受ける予想が出ています。
しかし、到達予想が90分以上あるので、落ち着いて建物に気をつけて歩いて帰ってくるように伝えています。(家が土砂災害の心配はない緩やかに山側なので海側から遠ざかる方向になり、これを水平避難と言います)
こんな風に家族と「ここは、こういうところだから、こんな風に行動したほうがいい」ということを決めておくと、どこへ迎えに行くのか、どこで待ち合わせにしているのかが決めやすくなると思います。
では、次回は「緊急時の行動計画を決めるために係る施設について調べる項目」についてお話します。
それでは、また(^_^)/~

