第2話 事業承継につながる、社長に「もしものことがあったら…」の対策
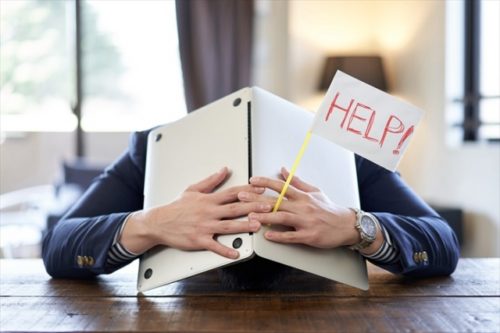 第1話では事業承継には「時間管理」が大切ですよ。というお話をいたしました。
第1話では事業承継には「時間管理」が大切ですよ。というお話をいたしました。
事業承継には肩書(権利関係)や財産、決算書には出てこない知的資産の引継ぎが必要で、とても時間がかかるということ。そして、社長に「もしも…」のことがあった場合に事業がストップしてしまわないよう備えておきましょう。というお話でした。
そして今回は、事業承継にもつながる、社長の「もしものことがあったら…」の対策について従業員がいることを前提で、具体的な手順をお話していこうと思います。
⑴ 社長の「日常業務の棚卸し」
事業承継への対策は先送りになってしてしまう社長でも、地震や台風の被害、新型コロナ感染症で何が起こるかわからない事態をたくさんご覧になったりしていると、自分に「もしも…」のことがあった場合について身近に感じられていることと思います。
では、その「もしも…」の対策とは何をすればいいのでしょうか?
それは…社長の「日常業務の棚卸しをすること」から始めていきます。

突然、社長が不在になっても経営が回るようにしておくというのは、「社長と同じ作業ができる人」を立てておくことが必要ですが、社長の「もしも…」に備えるということはそのまま「社長の交代」になる場合もあり、「一時しのぎ」のことではなく「代表者としての決裁権」は「後継者候補」にしてもらうように手を打っておくことが必要です。
ただ「後継者候補なんていないよ…」というところも多いでしょうから、その時は組織を引っ張っていけるキーマンをみつけておくことが必要ですね。それが、社内であるか社外にお願いするかで作業の量も変わってきます。
そして、社長業務の棚卸しをすると「グループ分け」をしていく必要があります。
「社長でなければいけない決裁権業務」と、社長じゃなくても「誰かがしなければ会社が回らない」…というものを分ける作業です。
⑵ 棚卸しの方法
まずは、社長が会社に出社してから1日のルーティーンをリストアップしていきます。
曜日によってすることが違うかもしれないので、1週間の動きを書き出して「見える化」していきます。
さらに1か月ごとにしていることは何か?
そして、月によっては注意しなければいけないことはないか?
もリストアップします。
(4月はこの手続きが必要で、8月はこの会合に顔を出さないとマズくて…12月はこれに時間がとられる…などなど)
そうして1年を通して定期的にしていることを把握します。
この1年スパンで見える化すると、突発的なことが起こっても大事な手続きをし忘れたり、
また、そのための時間を工面することがしやすくなります。
さらに、普段の業務と一緒に事業承継の準備も組み込んでいけます。
しかし、1年スパンで考えられないものもありますね。
事業の継続に「許可の更新」など忘れてはいけない手続きがないか、ということです。
1年スパンでないものもあるので、余白に「番外編」も〇年〇月とメモしておく必要がありますね。
リストアップをした後は、今すぐにでも引継ぎができるもの、できないもの(「もしも…の対策」にはムリクリでも引き継がなきゃいけないので準備していきましょう)を区別して、
後継者に渡さなければいけないものと、別の人でもいいものを分けていきます。
これは、事業承継に必要な社長の肩書(権利)の移動を意識して行っています。
⑶ 代表者であるための資格
注意しなければいけないことは、代表者であるために資格が必要ではないか?
ということです。
一人親方の建設業であれば、経営管理責任者の要件を満たす必要があり、経験年数がかかわってきますし、
医療法人であれば、代表理事は医師または歯科医師である必要があります。
私のように行政書士の資格が必要な業務でも、司法書士の先生ができたりする業務もありますので、
残された業務の割り振りは「知っている人」でないとできないものがあります。
やはり社長ご自身が社長業務の引継ぎを考えなければいけません。
つまり、すぐに社内で引き継ぐことができない事情が出てくるかもしれないということです。

社外からヘッドハンティングすることや、同業者に引継いでもらうことも考えますが、
すぐに見つかるかどうかわからないですし、顧客を失うこともあります。
⑷ 会社のものは社長のもの…
中小企業では社長個人名義の不動産を使って会社が運営されている場合もあり、
社長が会社に運営資金を貸している場合もあります。
その絡み合っている部分について丁寧にはがしていく作業が必要です。
「一時の代理」だけで乗り越えられない「社長の突然死」などの場合を考えると、
社長個人名義の財産の引継ぎも会社の一大事として考えなくてはいけません。
(遺産分割で会社権利が分散されないためです)
後継者が現社長の持っている会社の財産をすべて引継ぐことになると(権利の集中を図るため)
その評価額が高ければ、お金に換えてしまうわけではなくても、
「あの人だけたくさんもらってる…」と感じる相続人もいるでしょう。
その方に丁寧な説明をして、納得していただき、
その分、他の財産を渡す計画を考えなければなりません。
争族にならないための対策ですね。
ここに、会社からの退職金を考えたり、保険を使うことを考えたりします。
⑸ 社長のものは会社のもの…?
細かいところですが、個人口座が閉鎖になった場合に何が困るのか?
会社名義のカードがなくて、個人のカードで支払った出張費の請求を
会社にしなきゃいけないとか、
携帯電話の契約をすぐに解約してしまってもいいのか
(古い友人で名義株主の連絡先が入っているかもしれない…)など、
社長個人の財産の行方も整理しておかなければいけません。
しかし、プライベートな部分を全て「あからさま」にしてしまいたくないでしょうから、
「シークレットリスト」としてご自分だけの「見える化リスト」を用意し、

そこから社長自身でどのように処分するといいのか書き残しておくと安心ですし、
社内で困るようなこともないでしょう。一種、遺言に近い感じになりますね。
社長の交代が突然起こってしまっても、
今まで積み上げた体制が揺らいでしまわないために、
家族が困ることもなく、さらに盤石な社内体制にしていくための作業として、
社長の「もしも…対策」からいろいろ「やらなきゃいかんな…」というものが
見えてくるのではないでしょうか。
今回のお話は従業員がいることを前提でお話をしていますが、
次回は、私のような「一人親方」の社長がしておく「もしも…」対策
についてお話をしようと思っています。
それでは、今日はここまで。

