第18話「えい!やー!」で進めてしまう事業承継

事業承継は計画を立てて進めていくことが好ましいですが、そんなことも言っていられない場合があります。
社長の突然の病気の発覚や事故などで引退を余儀なくされることや、突然お亡くなりになってしまう事態が発生した場合です。
このような時は、とやかく言っても仕方がない…と突貫工事的に「社長の不在」をなくすために事業承継を進め、あとから不都合な点を従業員との間でトラブルが起きないように進めていく必要があります。
⑴ 社長のもしも対策ができていない事業承継のつまづきポイント

トラブルというのは、従業員の雇い入れた契約や取引先との約束事をこちら都合で突然了解もなく変更してはいけませんし、「今までのやり方」と違ったことを後継者が突然やり始める(例えば人員整理など…)ということも、してしまうと社員がついてきてくれないこともあるので注意しなければいけません。
そして、社長不在の「もしもの対策」ができていないことで、必要以上に後継者に資金面での負担が大きくのしかかる場合もあります。
事業承継時では財産の引継ぎに関して税金の負担や、思ってもみないタイミングでの高額な株式を引き取らなくてはいけない場合もあります。
事業承継士は手続きの中で引継ぐ資産をできるだけ負担の少ないように、引継ぐタイミングを創り出すこともしますが、そのような創り出すタイミングがないまま「えい!やー!」で進めていく事業承継では「事前にやっておけばよかった…」とタイムオーバーで妥協するところも出てきたり、必要のなかった資金を用意しなければいけないこともあります。
⑵ 古参社員と後継者の関係
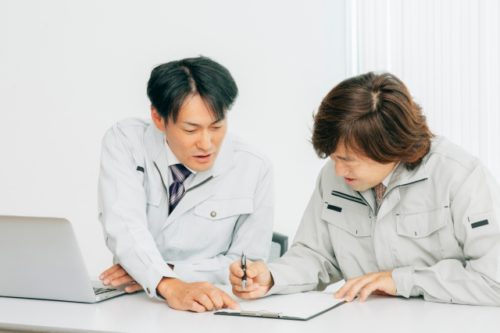
前社長との関係が長い古参社員は「今までと違うこと」を嫌うこともあり、後継者のやり方を受け入れてくれない場合があります。
そのような組織の歯車がうまく回りださない場合は「うまく回る手段」を考えなければいけません。もちろん、後継者も劇的な改革をするのではなく、一旦「社長不在」を何とかすることに専念し、自分好みの経営については徐々に進めていく方法がスムーズに事業のバトンを引き渡すことができるでしょう。
会社の収益には社長の「決断するスピード」が遅ければ機会を逃すこともあり、決断しても動き出さないということが起こると、承継後の収益は落ちてしまうこと間違いなしです。
後継者が未来へ繋ぐ組織作りには、後継者の右腕となる相談相手が必要です。
そこに、古参社員がついてくれると心強いですが、非協力的であれば新しく後継者の右腕を見つけ、育てるしかありません。
⑶ 後継者に引継ぐ前にしておくべきこと

後継者の時代に変わる前に、あらかじめ古参社員の待遇や役割を考えておかなければなりません。
走り続ける会社運営のスピードを他社との競争に負けてしまわないように、技術を持つ社員であるか、取引先や顧客との人脈に力を発揮してくれる社員であるのかなど、それぞれの役割をうまく新社長の体制でも活かせるように配置しなければなりません。
古参社員の非協力的な時間が長ければ力を貸してもらうこと自体を諦めなければいけなくなります。
⑷ 退職金を支払うのは引退する社長だけではなかった

突然引退をする社長には退職金の支払いを考えますが(役員の退職金規程がなければ作っておかなくてはいけませんね)社長と一緒に辞める決断をする古参社員や役員もいるので、長きにわたって働いてくれている人のためにも退職金が必要になります。
これが「えい!やー!」で資産の引き継ぎにかかる買取りの費用や税金の費用の他、さらに退職金の負担が一気にのしかかるため、もしも対策ができていないと資金繰りが大変になることがあるのです。
会社の力になってもらえるような古参社員の引き留めができるのか、うまく折り合いが取れずに退職金の準備をしなければいけないのかによっても、後継者の負担も大きく変わり、また、引継いで社内体制がうまく回り始めるのかも、社外の人の目にも見えてくることになるでしょう。
社長の平均年齢も少しずつ高齢化になっていますが、できれば60歳を過ぎると早いうちに社長はしっかり「自分の引退」についての準備に取りかからなければいけないと思いますね。
それでは、今日はここまで。

