第23話 事業は石橋をたたいて渡っていられない。

危険なことはしない。
これは誰にだってできること。動物でも、亡くなっている人もできること。
なぜなら、動かなければ危険なことはしていないという考えだそうです。
事業はいろいろな選択で危険が伴うものです。経営環境や人事など、スピードよく決めなければいけない場合があります。そのような時に石橋をたたいてじっくり考えることができない場合も多々あります。
従業員の中には、毎日決まったルーティーンをこなすことで危険なことの判断を迫られなければ、時間は過ぎてお給料が入る。そのように考える人もいるかもしれません。
それも1つの選択をしているのです。その選択の場面で「安全なことする」を選ぶ人が多いのだろうということです。
⑴ リーダーの選択はギリギリを間違えないということ。
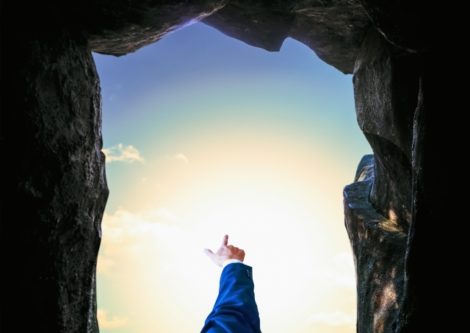
リーダーの後ろに続く従業員に対して、安全な選択をして引っ張っていかなければ、人はついてきてくれないでしょう。(たまに、新たな挑戦に「思い存分突き進みましょう!」といってくれる従業員もいるでしょうけれど)
「家族がいるから」とか、自分の未来を天秤にかけて「どっちが安全?」と考えると思います。
リーダーのところには簡単な選択肢はきません。例えば90:10で安全な方が分かっているのであればきっと90を部下でも選択して進めていけるでしょう。
リーダーは常にギリギリの選択をし続けていくことになります。
新規開拓に今出ていくべきか?
既存の事業を売り渡して業務縮小をして会社体力を戻すか?など…
答えが見つからないような「51:49」という選択肢が出てきた場合ちゃんと51を選べるリーダーにならなければいけません。
⑵ 事業承継のタイミングで選択するものとは?

後継者を選択する。持分や株式をどれくらい誰に渡すのが会社が安泰するのかを選択する(決める)。後継者の外部に紹介すること(デビュー)はいつにするのかを選択する。後継者に反抗的な従業員をどのように考えるのか、事業承継を機に新たな役職を考えたり、部署を変えてみたり、技術があっても定年を機に辞めてもらうのか…を選択する。などなど。
事業承継のタイミングでは、会社の未来を繋いでいくために51:49の選択肢がたくさん出てくることでしょう。
⑶ 後継者の選択肢に右腕の存在

会社の権限を持ち、難しい場面での51:49を間違わずに51を選択し続けられるように、後継者も感覚を研ぎ澄ませなければいけません。
そのためには常に自分の頭で考え、従業員がついてくるのか、競合他社との競争に勝てるのか、環境の変化についていけるのか…などリーダーとして勝てる判断が出来なければいけません。重要なところを人に任せると「お飾り社長」になってしまいます。
石橋をたたいて渡るような時間がない場合は多々あります。このような時には自分の情報が不安な場合もあるでしょう。その場合に備えて参謀として信頼できる右腕を持つことも51:49の判断に必要なことです。
リーダーは孤独だという人もいます。しかし、ギリギリの選択肢で石橋をたたいている暇がない場合のためにも「右腕」となる参謀の力を持っているということは、より会社としては盤石になるのではないでしょうか。
すでに走り続けている会社の中には、会社のことをよく知り右腕となる「光る原石」がいるかもしれませんし、外部からの助っ人を入れることもできるでしょう。
経営トップのYESマンとなる人では無理ですが、信頼できる人材を見つけておくことも先代社長が築き上げた組織を途中から引継ぐ後継者には必要なことだと思います。
それでは、今日はここまで。

