第26話 医業の承継は地域にも切実な問題
 医師の偏在や不在地域などは以前から対策すべき問題となっていて、厚労省でも医師の確保計画を立てたり偏在などの実態を見える化をしたり、医学部の募集人数配分を医師の少ない区域へ向けることや、へき地での医療経験が後のキャリアアップに繋げられるようにするなど、いかに医師の不在地域を何とかしなければ…と対策を進めているところです。
医師の偏在や不在地域などは以前から対策すべき問題となっていて、厚労省でも医師の確保計画を立てたり偏在などの実態を見える化をしたり、医学部の募集人数配分を医師の少ない区域へ向けることや、へき地での医療経験が後のキャリアアップに繋げられるようにするなど、いかに医師の不在地域を何とかしなければ…と対策を進めているところです。
しかし、せっかく医師が着任したとしても、そこから後継者問題を解決していかなければやはり医師の不在が問題になってしまいます。
⑴ 医師不足という地域

全国での医師の後継者不足は70%を超え、他業種を入れた業種別でみると平均61.5%をはるかに超えて切実な問題になっており対策を打たなくてはいけません。(2021年帝国データバンク調査)
まずは、医師の少ないところに医療不足がないようにすることですが、医師が着任した後も丁寧に後継者不在にならないためのサポートも必要だと考えています。
医療の提供をしながら、診療所の経営に係る数字を把握することや患者さんやスタッフを引き継いでいくこと、そして引継ぐ資金の準備(税金の準備など含めて)の他、行政向けの許可や届け出の手続きなど、何をどのような順番で用意していくのかを段取りすることは、とても大仕事になるので、医療機関の後継者問題には積極的に地域の行政機関や医師会などが相談窓口などを設けてあげることも必要だと思っています。
⑵ 「人の想い」を引継ぐということ

私が「丁寧に」時間をかけて…と、考える部分は特に「人」に係る引継ぎになります。
例えば、個人の診療所の院長が親子間で引継いでいくとして、気にかけていただきたいことは親子であっても後継者教育という「時間」を取る必要があるということです。
医業承継を考えるには経営面と診療面に分けて考えていく必要がありますが、診療面にあたる「人の想い」を引継ぐということは、精神的に大変だということも知っておく必要があります。
1つは院長の診療方針と後継者の「どのような医療機関にしていきたいか」が違うことは当たり前だと考えなければいけません。
今までの患者さんを引継ぐためには、やはり前任の院長先生の方針からガラッと変えていくわけにはいかないのです。もちろん同じ診療科目があることも重要です。
そして、今まで従事してくれていたスタッフへ信頼を寄せている患者さんもいることでしょうから、スタッフとの関係も良好に従事してもらえることも大切です。急に労働体制を変えてしまうなど、居心地が悪くなるようなルールを作っていかないことも大切ですが、今まで不満を抱いていた労働環境を修正していくことも後継者として気に留めていただきたいところです。
医業承継では、患者さんのカルテが引継がれても、今までのように安心できる診察かどうか「患者さんの満足度」を考えておかなくては、せっかく引継いでも別の医療機関に移っていかれると報酬が入ってこなくなります。
親子で承継ができたとしても、「院長の子供だから大丈夫だろう…」という容易な考えでいてはいけません。人によって合う・合わないがあるので、第三者への承継も親子での承継も「人」の引継ぎに関して新参者として同じように考えた方がいいかもしれません。
⑶ 丁寧にすることで防ぐ医療過誤
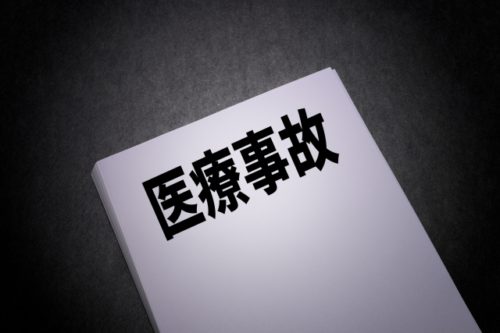
長年、院長先生に診てもらうと、「院長先生は言わずにちゃんと分かってもらえた…」と、もしかすると、そこからヒヤリ・ハットや医療過誤につながる事案も出てくるかもしれません。
症状の強弱や薬の合う・合わないなど、同じ風邪であっても症状が一人一人違う点で対応も違うと言われますので、後継者としては、まずは「言わずに分かっていたことでも、言ってもらえる仲」を築いていかなくてはいけません。このようにトラブルなく診療を続けていくためにも、後継者が院長先生の診ていた患者さんやスタッフ、取引先や連携医療機関などもうまく引継いでいけるように下準備が必要になります。これが「後継者教育に時間がかかる」ということです。(まだまだ財務のことなど引継ぐための時間も必要ですし…)
どうしても肉体的な衰えを感じて診療所の引継ぎを考えるケースが多いのですが、あまりに高齢になって引継ぎの準備をし始めると、診療を引継ぐだけでも時間を要しそうなので、余裕をもって、できれば承継後も診察を少し続けられるくらいの体力も残して、進めていくようにすると引き渡す院長も安心できる引き際のタイミングで引退できるのではないでしょうか。
それでは、今日はここまで。

